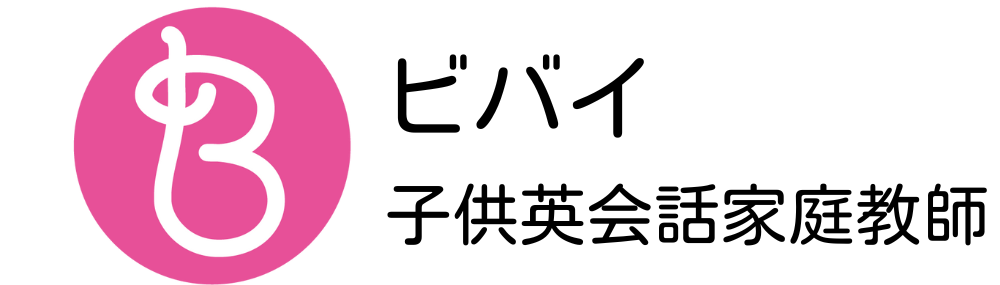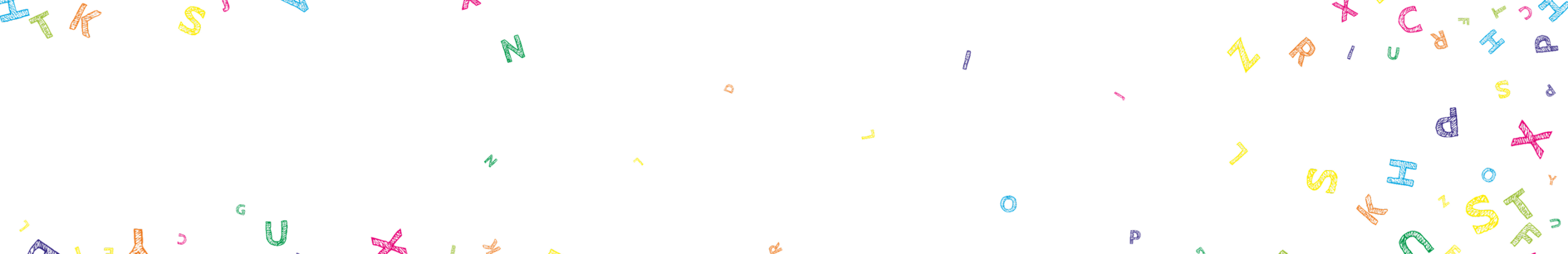寒さが少しずつ和らいで来ましたね。受験シーズンも一段落しましたが、毎年、特に首都圏では、電車には塾や予備校の宣伝広告が溢れ、単語帳を握りしめた児童や生徒が多く見られます。
私は、元々は中学、高校、大学受験の講師として教壇に立っていました。これまで担当してきた教え子の数は万を超えていますが、誰一人として同じような受験はありませんでした。
私自身、中学受験を経験し、中高一貫校で育ちました。非常に多くの刺激があり、現在の私を支えている経験の一つではないかと思います。私は、中学受験には条件付きで賛成の立場ですし、過去の動画でもそのように発信をしておりました。
1月~3月は、中学受験を視野に入れ、習い事を整理していく時期になります。この時期は、毎年ビバイでも多くの方が入会をする時期でもありますが、同時に中学受験に専念するとのことで、退会される方も数名おられます。
習い事を続けるか、辞めるかという決断は、とても勇気がいることですし、双方にメリット、デメリットがあり、それらを天秤にかけて保護者様は判断をしていくことでしょう。
今回は、中学受験と英会話に関して、どのような天秤を持ってそれらを判断すればいいのかという視点で記事を書いて見ました。悩める保護者様の参考になれば幸いです。
1.英会話学習は継続しないと意味がない
英会話学習に関して、絶対的に覚えておいてほしいことがあります。それは、「英会話の勉強を1度始めたなら、死ぬまで続けること」をお勧めします。死ぬまで、というのは極端な言い方ですが、「もう今後の人生で二度と英語を使うことがないだろう」という時まで、という意味だと解釈してください。
英会話に関しては、触れなくなった瞬間から能力が落ちていきます。人間の脳は使用しない領域はどんどんフォーマットしていきます。英会話のように、日本では、日常でほぼ使われないものはキレイに消えていきます。例えば、小学校に入る前に英会話を習ったお子さんが、急にそれを辞めたとします。1年も経てば、リスニング・スピーキングの能力だけでなく、語彙力も急激になくなっていき、1年前とは比べものにならないくらい英語ができなくなっていくのです。
せっかくお金をかけて英会話を習得させたのに、それがほぼ0になる。これは教育費の無駄だと私は思っています。余談ですが、私が講演会でお話をさせて頂くとき、教育にかかるお金の話をします。
大学卒業まで「これくらいのお金がかかりますよ」といった話をすると、皆さん驚いた表情をされます。そして、少しでもコストパフォーマンスを上げたいのならば、手段は2つあります。1つは「世帯収入を増やす」、もう1つは「無駄をなくす」ことです。この「無駄」というのは、まさに途中まで学習していた英会話の学習をストップするようなことです。そうであるなら、最初からそんなものにお金と時間をかけずに、家族で会話をしていた方がいいのではないかとすら思います。
英会話の学習とは、植物を育てることに似ています。水やりをしなくなれば、枯れていくように、学習を辞めた時点でどんどんゼロに近づいていきます。逆に、数学や国語力、社会や理科の知識などは、建築物に似ています。多少のガタツキや老朽化、流行り廃りなどがあるとはいえ、英語のように無に帰することはあまりありません。理由は、これらは恒常的に触れるものであり、小中高の12年間に渡って目にし続けることになります。しかし、英会話に関してはやらなくなった瞬間から触れることがほとんどなくなります。私も中高と英語を勉強しましたが、それと英会話とは全く別物です。
中学受験と英会話学習のどちらが大切か、という二項対立ではなく、中学受験をさせることで英会話を辞めるのであれば、中学受験が終わってから英会話の学習を始めれば良いでしょう、ということです。当然、小さいうちから継続して英会話の学習をした子との差は生まれると思いますが、そこは中学入学後もさらに努力を継続し、追いついていくしかないでしょう。 逆に、英会話は絶対に続けさせるというのであれば、中学受験があろうとも絶対に続けるべきだと私は思います。当然、お子様の負担は増えていくと思いますが、英語の学習を週1回1時間くらいとり、毎日15分の音読をすることがそこまで大変でしょうか? 私が中学受験の指導をしていた経験上、寝る間も惜しんで勉強をしている多くの子供たちでも、親がスケジュールの管理を手伝うことで、それくらいの時間は確保できると思います。
しかし、子供達にそこまで無理をさせたくないと思う親御さんも多いでしょう。そうであれば、英会話の学習は後回しにして、中学受験を優先するという判断も間違いではないと思います。ですが、中学受験、いや、高校受験や大学受験も含めて、そもそも「受験をする」とはどういうことなのか、真剣に考えたことはありますでしょうか。
私はこの業界では珍しく、中学、高校、大学受験というすべての指導を経験しています。どれもが大手の塾・予備校で授業をし、第一線で生徒を合格へ導いてきた自負があります。そのような私の経験から、受験についてお話をしたいと思います。
1.どこにゴールを設定するのか
私自身の体験、そして、講師としての経験を踏まえてお話しさせて頂くと、英会話にしても中学受験にしても「なんとなくみんながそうだから」「やらせてないと不安だから」という理由で始められる保護者様が非常に多いように思います。特にお子様が小さい場合は、親の判断によって習い事を決定していくかと思いますが、意思決定の判断基準が非常に曖昧であるように感じます。
ビバイでも、私が初めて保護者様と面談させて頂く際「ゴールをどこに設定しますか?」という問いを必ずしています。もちろん、その回答は様々で「英語が楽しくなるように」というご要望もあれば「海外で通用するように」とおっしゃる方もおられます。
ビバイは家庭教師ですので、保護者様のご要望に沿って、最大限のカスタマイズをしてレッスンを提供しています。英検対策をすることもあれば、インターの宿題をお手伝いすることもあります。海外転勤が決まったので、猛スピードで会話のレベルを上げるようにレッスンを展開することもあります。
しかし、時に「そのゴールは本当にお子様のためになっているかな?」と感じた場合は、その旨をしっかり伝えるように心がけています。例えば「とにかく英語だけでレッスンを行い、早く英語に慣れるようにしてほしい」というご要望があった場合、年齢にもよってはお断りしています。例えば、小学4年生くらいの児童に、ひたすら英語でレッスンを進めても効率は良くありません。日本語で解説を加えることで、ストレスを軽減し、理解を助けてくれます。ビバイがバイリンガルの教師を多く揃えている理由もここにあります。
同様に中学受験に関しても、「本当にそれでいいのかな?」という保護者様とこれまで多く出会ってきました。
私は、受験で合格させるために必死に指導をする一方で、「落ちてもいいじゃん。全力でやったなら」と、思うようになっていました。もちろん、それで指導に手を抜いたことは無いと断言できますし、毎年毎年、合格発表のその瞬間まで、心から受かってほしいと願っていました。
しかしながら、現実は甘く無いもので、どれだけ必死に勉強をしても不合格になることはあります。それでもなお、必死にやった結果であるならば、その結果には価値があるものだと思っています。
私自身、中学受験の頃に第一志望の中学に不合格でした。大学受験でも、現役の時に不合格となり、浪人して志望していた大学に進学しました。私の中学受験の思い出ですが、第一志望校の合格発表の日は平日で、小学校の授業がある日でした。合格通知が自宅に手紙で届くのですが、休み時間の度に学校の公衆電話から自宅に電話をし、通知が届いていないか確認をしていました。
ご経験のある方ならご存知かもしれませんが、郵送で合否通知が来る場合、封筒の厚さで合否がわかります。合格の場合は、各種案内やその後の手続きに必要な書類が入っているので厚い封筒なのですが、不合格の場合は紙が1枚入っているだけですから、とても薄いのです。
何回目かの電話で、私の父が電話に出ました。「たぶん… ダメだと思う。」という父の言葉を聞き、どうしても自分の目で確認したい私は、昼休みにその通知を持ってきてもらいました。しっかりと自分の目で不合格を確認した後、父はその通知を持って仕事に戻りました。私はショックのあまり、誰とも話す気になれず、また授業を受ける気力もなくなったので、先生に相談し早退をさせてもらいました。家に帰り、ベッドに飛び込んでひたすら泣き続けました。しばらく経って、母から連絡を受けた父が家に戻ってきました。私の部屋を開けるなり、開口一番言った言葉が「なんをしよっか!!情けなか!!それくらいのことで学校を早退するような弱い人間になるな!!」と叱られました。
はっきり言って、この対応はまずいと私は思います。この記事をお読みの保護者様は絶対にしないでほしいと思いますし、事実この時の私は「お父さんは何もわかっていない!僕がこんなに悲しんでいるのに叱るなんて!」と、さらに辛い気持ちになりました。しかしなが、今では父のその時伝えたかった気持ちは理解できます。
父の名誉のために付け加えておくと、父は私の受験に関してもの凄く真剣に手伝ってくれました。父はずっと野球をやっていましたし、勉強とは無縁の少年時代を過ごしていました(笑)。当然、受験のことはおろか、勉強での相談などはできず、私も父に勉強の質問をしたことはほとんどありません(笑)。私も少年野球に入っていましたが、小学5年生のときにどうしても中学受験がしたいと思うようになり、少年野球を辞めて遠い塾に電車で通うようになりました。父としては、ずっと野球をしていた父は寂しい思いもあったでしょうし、祖父は「野球を辞めさせて塾に行かせるなんてあり得ない!」と、私の母に詰め寄ったそうです。ただ、父はそのようなことは一言も言いませんでした。土日にテストがある時は、私が電車で塾に行くのが大変だろうということで、いつも車で送ってくれていました。毎週のように、社会のプリントから問題を出してくれたりもしました。私の中学受験に対しては、母はもちろんのこと、父も真剣に向き合ってくれていました。
しかしながら、父にとっては合格するのも不合格になるのも特にどちらでも良かったのです。結果が大切なのではなく、その過程でどれだけ努力をしたが大切なのですから、父にとっては、私の不合格など「それくらいのこと」だったのです。社会に出ればもっと大変なことはたくさんあります。受験で不合格になったからといって死ぬわけではありません。「これから先、辛いことや努力が報われないことだってたくさんある。だけど、それを乗り越える強さを持て」という、不器用な父のメッセージであると、今は理解できます。もちろん、このような理解に至るまでには少し時間がかかりましたが。
私は、中学受験をはじめとするすべての受験において、「誰のための受験なのか。」「何のための受験なのか。」という2点を、親御さんには常に胸に刻んでおいて頂きたいと、強く願っています。
「『誰のためか?』って、そんなのは子供のために決まっている!」と皆さん口を揃えておっしゃるのですが、では「何ため」についてはいかがでしょうか?難関中学に合格することが、どのように「子供のため」になるのか、しっかりと説明できますでしょうか? 確かに難関中学・高校というのは、難関大学の合格者数も高いです。とはいえ、全員が合格するわけではありません。また、そもそも難関大学に合格すれば子供のためになるのかというと、そう単純なことではないことは、大人である皆さんがよく理解ができることでしょう。一流と呼ばれる大学の出身者で「〇〇大卒なのに…」と思った人に出会った経験があるのではないかと思います。
結局は、どんな中学や大学に行こうとも、その人本来の力を伸ばすことができない限り、どのような環境に飛び込んだとしても結果はさほど変わりません。難関中高一貫校というと聞こえはいいですが、所詮は中学・高校です。その環境で、大人として必要な能力をすべて養成できるわけではありません。むしろ、その環境に驕り「僕は〇〇中学・高校出身だ!」とか「私は〇〇大学出身なのよ!」という余計なプライドを持つことで、周りと軋轢を生む人だっています。
努力の結果としての合格は、当然賞賛に値します。けれどそれは、すべてに側面おいて価値を持つわけではありません。合格よりも価値のある不合格を経験する人だっているわけです。
私は、難関と呼ばれる中学・高校に進むメリットは「出会う人」だと思っています。それは、大学も同じで、やはり素晴らしいと思える人に出会えることが何よりもの財産だと考えています。子供が勉強をするかしないか、もとい「できるようになるかならないか」は、遺伝要因だけでなく、環境要因が大きく影響します。そして、環境要因とは、周りにいる人です。地理的な世界ではなく、人との繋がりの世界が広がったとき、人は新しい価値に出会い、刺激を受け、また新しい自分になるよう努力を始めるものだと思います。
逆に言うと、自分の子供が進学する中学の生徒や校風なども知らず「成績が上がればこの中学に入れたい」とか「進学率が高いからこの学校に入れる」といった理由は、私から言わせると大間違いです。私は運良く、これまで通ったすべての学校で周りの人に恵まれていたと感じます。しかし、逆にそうでなかった同級生や生徒たちも多く見てきました。そして、できることなら、どのような環境にあったとしてもしっかりと努力ができる人間が増えてほしいと願っていますし、逆説的ではありますが、そんな人はやはり一流と呼ばれている学校に進学し、そして社会でも活躍しているように思います。そして、そうなるために大切なことは、親がいかにそのような土台を作ってあげられるかにかかっているように思います。
受験をさせるときに一番大切なことは「親の考え方」です。特に、自分自身で意思決定をすることが簡単ではない中学受験は、親の考え方がとても大切になります。中学受験は「親子の受験」です。厳しい言い方を敢えてしますが、子供が中学受験をする前に、そもそも親自身が「子供に中学受験をさせる資格があるのか」を冷静に分析してほしいと、私は考えています。
中学受験を考えているお母さん、お父さん。あなたは「誰の」「何の」ために受験をさせるのですか?